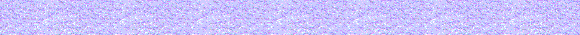仠惗曐揮姺惂搙偺儊儕僢僩丒僨儊儕僢僩乮1999擭11寧25擔乯
丂
(1)徚旓幰抍懱偺梫惪偱摫擖
丂惗曐偺揮姺惂搙偼丄乽巰朣曐忈僯乕僘偺憹戝傊偺懳墳乿傪巜揈偟偨曐尟怰媍夛摎怽傪庴偗偰丄徍榓50擭11寧偵摫擖偝傟偨丅徚旓幰抍懱乮墶昹僐儞僔儏乕儅乕僘僋儔僽摍乯偵傛傞壓庢惂搙摫擖傊偺梫惪偵墳偊偨傕偺偱偁傞丅偦偺慜擭49擭偵偼丄庡宊栺偺曐尟婜娫偺拞搑偱掕婜曐尟摿栺傪晅壛偟偰巰朣曐忈妟傪憹妟偡傞拞搑憹妟惂搙偑摫擖偝傟偰偄傞丅
丂偦傟傑偱偺挋拁栚揑偺梴榁曐尟庡椡偺帪戙偐傜丄巰朣曐忈傪廳帇偟偨掕婜晅梴榁曐尟庡椡偺帪戙傊偲堏傞拞偱丄暋悢偺曐尟偵壛擖偟側偔偰傕崌棟揑偵曐忈偑憹妟偱偒傞惂搙偲偟偰丄嘆摨偠曐尟庬椶偺傑傑巰朣曐忈傪憹妟偡傞拞搑憹妟惂搙偲丄嘇偄傑壛擖偟偰偄傞曐尟偺愊棫嬥乮愑擟弨旛嬥乯偲愊棫攝摉嬥傪壓庢傝壙奿乮揮姺壙奿乯偲偟偰丄怴偟偄曐尟庬椶偵揮姺乮宊栺撪梕偺曄峏乯偱偒傞揮姺惂搙偑摫擖偝傟偨傕偺丅
丂偲偔偵丄揮姺惂搙偺儊儕僢僩偲偄偊傞偺偼丄徍榓47擭埲崀幚巤偝傟偰偄傞摿暿攝摉乮庡偵丄捠忢偺攝摉偱偼惛嶼偟偒傟側偄娷傒塿摍偺忚梋嬥傪丄枮婜丒巰朣丒夝栺偵傛偭偰挿婜偺宊栺偑徚柵偟偨偲偒偵嵟廔惛嶼偡傞傕偺丅暯惉俀擭崰傑偱10擭埲忋宱夁屻偺宊栺徚柵帪攝摉偲偟偰愊棫嬥偵懳偟嵟崅65亾傕偺崅偄妱崌偱暐傢傟偰偄偨偑丄嵟嬤偼娷傒塿偺尭彮偵傛傝丄15乣17擭埲忋宱夁屻偺徚柵偵懳偟偰嵟崅32乣38亾偺妱崌偱暐傢傟偰偄傞亖愑擟弨旛嬥斾椺偺儈儏乕攝摉棪偺昗弨椺乯傪庴偗庢傞尃棙偑揮姺慜宊栺偐傜揮姺屻宊栺偵堷偒宲偖偙偲偑偱偒傞乮宱夁擭悢偑捠嶼偝傟傞乯揰偵偁傞丅丂丂
(2)挋拁宆曐尟偺乽摨宆揮姺乿偱峴惌巜摫
丂偙偺傛偆偵丄杮棃丄揮姺惂搙偼乽怴偟偄曐尟庬椶偵摿暿攝摉偺尃棙傪堷偒宲偓側偑傜曐忈偑憹妟偱偒傞乿偲偄偆崌棟揑側惂搙偩偑丄嶐崱丄塣梡塿偺掅壓偵傛傝僶僽儖摉帪傑偱懕偄偨俆亾埲忋乮嵟崅6.25亾乯傕偺梊掕棙棪偑傑偐側偊側偄媡偞傗忬懺偲側傝丄暯惉俆擭搙4.75亾丄俇擭搙3.75亾偲梊掕棙棪偑憡師偓堷偒壓偘傜傟傞拞偱丄惗曐夛幮偺媡偞傗晧扴傪宊栺幰偵揮壟偡傞偙偲傪慱偭偨惌嶔揑側揮姺偑峴傢傟偨偨傔丄暯惉俉擭侾寧丄戝憼徣曐尟堦壽挿柤偵傛傞乽梊掕棙棪堷壓偘嬊柺偵偍偗傞懳墳偵偮偄偰乿偺専摙埶棅暥彂乮巜摫暥彂乯偑惗曐嫤夛偵敪弌偝傟偨丅
丂偦偺庯巪偼嘆梴榁曐尟偐傜梴榁曐尟丄廔恎曐尟偐傜廔恎曐尟丄屄恖擭嬥曐尟偐傜屄恖擭嬥曐尟偲偄偭偨杮棃偺栚揑偵偦偖傢側偄挋拁宆曐尟偺乽摨宆揮姺乿傪帺弆偡傞偙偲丄嘇捛壛宊栺摍偲揮姺宊栺傪斾妑偟偰宊栺幰偵採帵偡傞偙偲丄嘊崅偄梊掕棙棪乮曐尟椏妱堷棪偵憡摉乯偺庡宊栺傪巆偟偰丄掕婜摿栺晅壛偵傛傞拞搑憹妟惂搙偺愢柧帒椏傪嶌惉偟丄宊栺幰偵愢柧偡傞偙偲乗偺俁揰丅峴惌巜摫屻丄惗曐夛幮偼拞搑憹妟偺愢柧帒椏傪嶌惉偟偨傕偺偺丄尰応儗儀儖偱偼幚嵺偵傎偲傫偳巊傢傟側偐偭偨丅
丂側偍丄曐忈宆曐尟偺掕婜晅廔恎曐尟偐傜掕婜晅廔恎曐尟乮嵟嬤偼崅攞棪偺掕婜晅廔恎偵擭嬥暐掕婜摿栺丒惗慜媼晅掕婜摿栺摍傪晅壛偟偨僞僀僾偑庡椡偩偑丄偄偢傟傕婎杮揑側曐尟庬椶偼摨偠傕偺乯偺乽摨宆揮姺乿偼丄曐忈傪奼廩偡傞傕偺偲偺柤栚偱偄傑側偍峴傢傟偰偄傞丅
(3)忔傝姺偊杊巭偱乽妱埨側弨桳攝摉彜昳傊偺揮姺乿傕搊応
梊掕棙棪偼媡偞傗妟偺奼戝偵敽偄丄暯惉俉擭搙2.75亾丄暯惉11擭搙2.0亾乮桳攝摉乯丄2.15亾乣2.5亾乮俆擭棙嵎攝摉丅夛幮偵傛傝堎側傞乯偲偝傜偵堷偒壓偘傜傟偨偑丄嵟嬤栚棫偮偺偼壛擖屻俀乣俁擭偺怴偟偄宊栺傪懳徾偵偟偨掕婜晅廔恎曐尟偺乽摨宆揮姺乿偱偁傞丅丂偙傟偼婛宊栺偺梊掕棙棪偑偡偱偵掅偄悈弨偵偁傝丄偐偮曐忈惈彜昳偱偁傞偨傔丄崙撪惗曐夛幮偵偲偭偰乽媡偞傗揮壱乿岠壥偼傎偲傫偳側偄丅偦偺栚揑偼晄嫷壓丄曐桳宊栺崅偺弮尭偵擸傓崙撪惗曐偑丄庡偵僇僞僇僫惗曐傗懝曐宯惗曐傊偺宊栺堏摦乮忔傝姺偊乯傪杊巭偡傞偲偲傕偵丄巰朣曐忈偺憹妟傪婇恾偟偰峴偭偰偄傞傕偺偲偄偭偰傛偄丅
丂暯惉俉擭丄11擭偺梊掕棙棪偺堷偒壓偘偵敽偄丄宊栺幰偺曐尟椏晧扴憹壛偵傛傞怴婯宊栺偺尭彮傪杊巭偡傞偨傔丄崅攞棪偺峏怴宆掕婜晅廔恎曐尟乮棙嵎懝傪掕婜摿栺晹暘偺旓嵎塿丄巰嵎塿偱寠杽傔偡傞偨傔偺彜昳偲偄偭偰傛偄乯傪庡椡偲偡傞崙撪惗曐夛幮偼丄掕婜曐尟晹暘偺曐尟椏傪戝暆偵堷偒壓偘偰偒偨乮掕婜曐尟偺掅椏壔乯丅傑偨丄梊掕棙棪偑掅偔妱崅姶偑偁傞斀柺丄攝摉枺椡偑敄傟偰偒偨嶰棙尮桳攝摉彜昳傪攧傝巭傔丄憡懳揑偵梊掕棙棪偑崅偔妱埨側弨桳攝摉彜昳傊偺愗傝懼偊傪恑傔偰偒偨丅
丂偙傟傜偵傛傝丄揮姺帪偺妱堷傕姩埬偡傞偲丄拞搑憹妟偡傞傛傝傕丄掅壙奿偺掕婜摿栺傪岤偔晅壛偟偨崅攞棪偺怴偟偄掕婜晅廔恎曐尟偵揮姺偟偨傎偆偑幚幙揑偵曐尟椏偑埨偔側傞働乕僗傗丄宲懕偡傞傛傝傕揮姺偟偨傎偆偑曐尟椏偑埨偔側傞働乕僗乮揮姺惂搙偱偼捠忢丄揮姺慜宊栺傛傝揮姺屻宊栺偺曐尟嬥妟偁傞偄偼曐尟椏偑忋偑傜側偗傟偽側傜側偄偺偱丄壖偵摨偠曐尟嬥妟偱揮姺偟偰傒偨応崌偺棟榑抣乯傕弌偰偒偨丅乮壓婰偺帋嶼椺嶲徠乯
仛帋嶼椺
乹婛宊栺乺桳攝摉丒10擭峏怴宆掕婜晅廔恎曐尟乮曐尟嬥妟3000枩墌乛庡宊栺廔恎晹暘200枩墌乯丂抝惈30嵨暯惉俉擭壛擖乮尰嵼俁擭宱夁乯曐尟椏65嵨暐嵪寧暐乮岥嵗乯曐尟椏侾枩1024墌
乲乽摨宆揮姺乿偲乽拞搑憹妟乿偺曐尟椏斾妑乴
嘆暯惉11擭乮33嵨帪乯偵丄忋婰婛宊栺傪10擭峏怴宆掕婜晅廔恎曐尟乮曐尟嬥妟4000枩墌乛庡宊栺廔恎晹暘200枩墌乯偵摨宆揮姺偟偨応崌丄摉弶10擭娫偺寧暐乮岥嵗乯曐尟椏偼侾枩2865墌丅
丂65嵨傑偱摨妟峏怴偡傞偲丄暐崬曐尟椏憤妟偼963枩768墌丅
丂65嵨帪偺僉儍僢僔儏僶儕儏乕乮夝栺曉栠嬥乯偼147枩2600墌丅
嘇暯惉11擭乮33嵨帪乯偵丄忋婰婛宊栺偵掕婜摿栺1000枩墌傪拞搑晅壛乮憹妟乯偟偨応崌乮拞搑晅壛偡傞掕婜摿栺偼婛宊栺偺峏怴帪偵曐尟婜娫傪崌傢偣側偗傟偽側傜側偄偺偱丄40嵨傑偱俈擭丄50嵨傑偱10擭丄60嵨傑偱10擭丄65嵨傑偱俆擭偒偞傒偲側傞乯丄摉弶俈擭娫偺寧暐乮岥嵗乯曐尟椏偼婛宊栺晹暘侾枩1024墌亄拞搑晅壛掕婜晹暘2870墌亖侾枩3904墌丅
65嵨帪傑偱摨妟峏怴偡傞偲丄暐崬曐尟椏憤妟偼996枩3096墌丅
65嵨帪偺僉儍僢僔儏僶儕儏乕乮夝栺曉栠嬥乯偼135枩3600墌丅
乲摨偠曐忈妟偱偺乽摨宆揮姺乿偲乽宲懕乿偺曐尟椏斾妑乴乮棟榑抣乯
嘆忋婰婛宊栺傪摨妟丒摨宆揮姺偟偨応崌丄掕婜摿栺晹暘偺掅椏壔偵傛傝寧暐乮岥嵗乯曐尟椏偼侾枩243墌
65嵨傑偱摨妟峏怴偡傞偲丄暐崬曐尟椏憤妟偼742枩1688墌丅
丂仸捠忢丄乽摨妟揮姺乿偼偱偒側偄偺偱棟榑抣丅
嘇婛宊栺傪偦偺傑傑宲懕偟偨応崌丄寧暐乮岥嵗乯曐尟椏偼侾枩1024墌丅
65嵨傑偱摨妟峏怴偡傞偲丄暐崬曐尟椏憤妟偼784枩176墌丅
乮係乯朄夵惓偟愢柧媊柋傪婯掕
丂帒嶻塣梡擄偱摿暿攝摉偑埑弅偝傟偰偄傞拞丄尨懃榑偱偄偊偽丄梊掕棙棪偺崅偄婛宊栺傪掅偄怴婯宊栺偵揮姺偡傟偽幚幙揑偵曐尟椏偑傾僢僾偡傞偺偱儊儕僢僩偼柍偄丅偨偩偟丄忋婰偺傛偆偵丄暯惉俉擭搙埲崀偺曐忈宆惗柦曐尟偺摨宆揮姺偵偮偄偰偼丄巰朣曐忈偺憹妟傪朷傓宊栺幰偵偲偭偰偼曐尟椏晧扴偺寉尭偑恾傟傞働乕僗傕偁傝丄廫攃傂偲偐傜偘偱偡傋偰偺摨宆揮姺偑埆偄偲偄偆斸敾偼揑傪幩偰偄側偄丅傑偨丄梊掕棙棪忋徃嬊柺偱偼丄揮姺惂搙偼桳岠側儕僼僅乕儉庤抜偲側傞丅
丂嵟嬤偺揮姺傪傔偖傞僋儗乕儉偱丄徚旓幰丒宊栺幰懁偐傜尒偨嵟戝偺栤戣揰偼丂嘆塩嬈怑堳偺愢柧晄懌丄嘇宊栺幰偑帺屓愑擟偱桳棙晄棙傪敾抐偡傞偨傔偺婛宊栺偺梊掕棙棪摍偵娭偡傞惗曐夛幮偺僨傿僗僋儘乕僕儍乕偺晄旛丄傪娷傔偨忣曬採嫙偺晄懌偵偁傞丅
丂嬥梈娔撀挕偼丄暯惉11擭10寧丄揮姺惂搙偵娭偡傞忣曬採嫙偺奼廩傪庯巪偲偟偰丄曐尟嬈朄巤峴婯懃乮憤棟晎椷丒戝憼徣椷乯傪夵惓丄岞晍偟偨丅偟偨偑偭偰丄夵惓婯懃巤峴屻偼偦偙偵惙傝崬傑傟偨愢柧媊柋傪懹傟偽曐尟嬈朄堘斀偲側傞丅
仛嬈柋塣塩偵娭偡傞慬抲乮嬥娔挕乯
丂曐尟嬈朄巤峴婯懃戞53忦傪夵惓偟丄曐尟夛幮偵埲壓偺慬抲傪島偠傞偙偲傪媊柋晅偗傞丅
丂曐尟宊栺偺揮姺偵嵺偟偰丄惗柦曐尟曞廤恖傑偨偼懝奞曐尟曞廤恖偑曐尟宊栺幰偵懳偟師偵梘偘傞帠崁傪婰嵹偟偨彂柺偺岎晅偵傛傝愢柧傪峴偆偙偲傪妋曐偡傞偨傔偺慬抲丅
丂嘆怴婯宊栺偍傛傃婛懚宊栺偵娭偡傞曐尟嬥妟丄曐尟椏丄曐尟婜娫偦偺懠廳梫側帠崁乮摉奩帠崁偺彂柺傊偺婰嵹曽朄偼丄尨懃偲偟偰揮姺慜屻偺撪梕傪懳斾偡傞曽朄偵傛傞乯丅
丂嘇曐尟宊栺幰偑婛懚宊栺傪宲懕偟偨傑傑昁梫側曐忈撪梕偺尒捈偟傪峴偆偙偲偑偱偒傞帠幚偍傛傃偦偺曽朄丅
仛帠嬈曽朄彂摍偺怰嵏婎弨
丂戞53忦傪夵惓偟偰怴愝偡傞忋婰偵梘偘傞彂柺傪曐尟宊栺幰偑庴椞偟偨巪傪彁柤傑偨偼墴報偵傛傝妋擣偡傞庤懕偒偑柧妋偵掕傔傜傟偰偄傞偙偲丅
丂***杮峞偺柍抐堷梡丒巊梡偼挊嶌尃丄斉尃怤奞偲側傝傑偡丅昁偢挊嶌幰偵嫋戻傪媮傔偰壓偝偄***